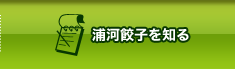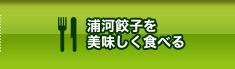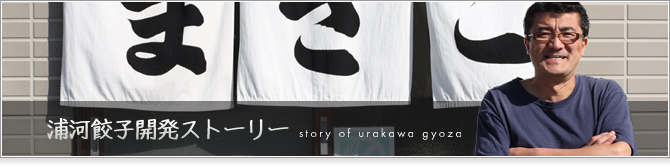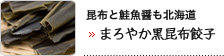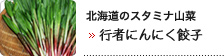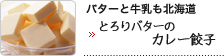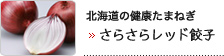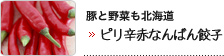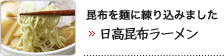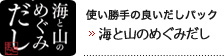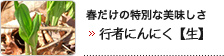「浦河は水も食べ物も美味しい。そして山あり海ありで最高の場所ですよ」
と屈託のない笑顔で話すのは、ラーメン店「まさご」店主の大久保直幸。
浦河餃子は、北海道浦河町で生まれ育った大久保によって作り出されました。ここでは、大久保が現在の浦河餃子を作り出すまでのストーリーと、餃子に包んでいる浦河への、そしてお客さまへの気持ちをご紹介します。
大久保がラーメン店「まさご」を開店させたのは平成8年のこと。
高校入学を機に東京へ移り、札幌で社会人を経験した後、Uターンで生まれ故郷である浦河に戻った大久保は、当初「まさご」で通常の餃子をお客さまに提供していました。
そんな「まさご」の餃子に浦河町・北海道の色合いが重なるようになったきっかけは、春の日高山脈に自生する行者にんにくです。
行者にんにくは、濃い味と香り、そして高い栄養価が人気の山菜。お店を訪れたお客さまとの会話のなかで、大久保はこの行者にんにくを餃子に活かすことを考え、当時北海道大学に在籍していた専門研究を行う先生に連絡を取り、アドバイスを求めます。

「行者にんにくの加工をしているのですが…と相談してみると、塩の配分であったり、調理法であったり、行者にんにくの風味や栄養価を活かす助言を頂くことが出来ました」
第三者の科学的な意見を取り入れながら、浦河餃子の一品目となる「行者にんにく餃子」が完成。
こうして、まさごの餃子に少しずつ浦河町・北海道の特色が宿るようになります。

浦河の山の幸「行者にんにく」を餃子に取り入れた大久保は、次に浦河の海の幸を餃子に活かすことを考えます。
浦河町は太平洋に面した海産物の宝庫。何より北海道三大昆布のひとつ、日高昆布の産地です。
この浦河特産の日高昆布を餃子に取り入れようとした大久保は、昆布の風味を引き立たせるため、東京では1玉200円前後の値を付ける高級玉ねぎ「さらさらレッド」を組み合わせの食材として選びます。
餡には、刻んだ日高昆布とさらさらレッドの旨味。さらに皮にも昆布を粉末にして混ぜて風味を利かせる。
こうして浦河餃子の2品目となる「ひぐまの黒ぎょうざ」が生まれました。
その後、さらさらレッドを中心にした「さらさらレッド餃子」や北海道産のバターやミルクを利用した「とろりバターのカレー餃子」など餃子の種類は増えていきますが、「北海道に、浦河に暮らす者として極力この土地の食材を取り入れていきたい」という大久保の意思は、どの餃子にも貫かれているのです。

しかし浦河餃子の特徴は、ただ単に「北海道の食材を使っている」という点だけではありません。餃子に入れている「量」がまた大きな特徴なのだと大久保は続けます。
「餃子の機械メーカーの人がやって来た時、私が餃子に使っている材料の量を見て『全国に機械を納品しているけれど、こんなに材料にお金をかけているところはないですよ。もっと使用量減らした方がいいですよ』って言われました(笑)」
同様の指摘は、餃子作りに携わるパートの方からも。

「『マスター昆布入れすぎじゃない?行者にんにくも入れすぎじゃない?』って言われますけど『いや、そのままでいい』と。私は量を減らそうとは思いません」
日高昆布を使っている、行者にんにくを使っていると謳えれば、その美味しさや風味を感じることが出来なくていいのかもしれません。利益のことを考えれば、量を減らすことが正解なのかもしれません。
しかし、頑なに減らすことはしない。
「これでもか!」と北海道の美味しい食材をたっぷりと使うからこそ、浦河餃子の美味しさがあるのだと大久保は力を込めます。
ラーメン店まさごがある浦河町も、他の多くの自治体と同じように近年人口の減少傾向が続いています。
「お店で接客していてもお客さんから『浦河を離れることになって…』という話を聞くことが多くて。地元で暮らす人間としては、やっぱり寂しいね」
過疎が進む町の状況を前に、移住アドバイザーなど具体的な活動を行う傍ら、餃子を通して浦河を知ってもらえたなら、浦河に興味を持ってもらえたら、と餃子に「浦河」の名を入れたのも、地元で暮らす者としての気持ちがあってのこと。
「近くに住む子供たちが毎日のように来てくれるんだけど、『おじさん、美味しかった』って言われるとやっぱり嬉しい。北海道や浦河の美味しい食材をふんだんに使っているし、今後は日本全国の方に喜んでもらえたら、そして餃子がきっかけになって、旅の途中にでもいいから浦河に来てもらえると本当に嬉しいね」